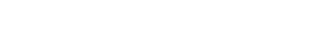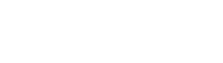- ■
せいぶれいえんコラム
- 2025/10/08
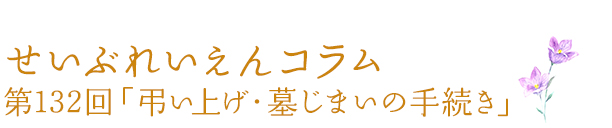
こんにちは、西部霊苑です。お墓参りや季節のことなど、何かのお役にたてる情報を発信していければと思います。
今回は「弔い上げ・墓じまいの手続き」についてお話しさせていただきます。
【弔い上げとは】
弔い上げは亡くなった故人が無事に成仏することを願い、お墓や仏壇などで供養する期間の終わりのことを言う仏教の考え方です。この期間というのは宗派やそれぞれの家庭により異なり、三十三回忌までとされることが多いようですが、十七回忌までの場合や五十回忌までとする場合もあります。
また浄土真宗では亡くなって即成仏するという考えのため、その後の法要は仏様に対してお経をあげるといった意味合いで行われます。
また神道にも弔い上げと同様の考え方があり、おおよそ亡くなってから50年目の五十年祭を弔い上げとするようです。
またお墓のカロート(納骨室)がいっぱいになり骨壺を保管する場所が取れなくなった場合にも同じく弔い上げをする場合もあります。
弔い上げのタイミングは残された遺族の考え方により自由な部分がありますので、よく話し合い納得をした上で行うようにしましょう。
具体的にはお墓や仏壇などに収めている故人に対し弔い上げの読経、位牌の閉眼供養などを行い、遺骨をお寺の合同墓や永代供養に任せるなどを行います。
この際、場合によっては改葬許可申請などの役所への手続きが必要になるので注意が必要です。
【合同墓や永代供養とする場合】
お寺で合同墓や永代供養とする場合、通常の遺骨の保管場所の移動と同じく改葬許可申請が必要になります。市役所などで改葬許可証を取得し、お寺などへ届ける必要があります。
【カロートへ散骨する】
お墓の下の納骨室に土の部分がある場合、骨壺の中の遺骨を土に還すことが出来ます。
遺骨を干し、細かく砕いたのち土の部分に還します。
この際には遺骨を保管する場所が変わるわけではないので改葬許可の手続きは不要のようです。
位牌はお寺などで供養してもらうことも出来ます。遺骨を入れていた骨壺も同じく供養してもらうことも出来るようですが、お寺によってはそのままご自身で一般的なごみとして処分しても大丈夫という風に言われることもあるようです。
【散骨する】
散骨する場合改葬許可の手続きは必要な場合とそうではない場合があります。
火葬後お墓に収めることなく散骨する場合は必要ないようですが、お墓に収めたのちの散骨であると必要とされるようです。
また遺骨を保管する場所が変わるという改葬の定義には当たらないため改葬許可証が発行できないとされることもあるので役所など自治体の窓口に確認するのがよいでしょう。
また散骨自体は法律的に行ってよいとされていますが、遺骨をそのままの形で散骨してしまうと遺骨遺棄罪となってしまいますので、必ず粉骨をすると共に散骨してよい場所かどうかを確認し節度をもって行うようにします。
他人の私有地や公共の水源にあたる場所などは避けましょう。
また散骨を依頼できる業者などに依頼する場合、改葬許可証を求められる場合があります。
【墓じまい】
今回は弔い上げについてお話しましたが墓じまいの場合でも同じくその後の遺骨の扱いによっては同じように改葬許可の手続きなどが必要になります。
それでは次回コラムもよろしくお願いいたします。

バックナンバー
-
- ■
せいぶれいえんコラム
- 2025/10/31
- ■
-
- ■
せいぶれいえんコラム
- 2025/08/27
- ■
-
- ■
せいぶれいえんコラム
- 2025/07/31
- ■
-
- ■
せいぶれいえんコラム
- 2025/07/02
- ■
-
- ■
せいぶれいえんコラム
- 2025/05/28
- ■
アーカイブ
- 2025年10月 (4)
- 2025年8月 (2)
- 2025年7月 (4)
- 2025年5月 (2)
- 2025年3月 (4)
- 2025年1月 (2)
- 2024年12月 (2)
- 2024年11月 (4)
- 2024年9月 (4)
- 2024年7月 (4)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (3)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (3)
- 2023年10月 (2)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (4)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (3)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (2)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (2)
- 2022年4月 (5)
- 2022年3月 (5)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (3)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (3)
- 2021年3月 (4)
- 2021年2月 (3)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (5)
- 2020年8月 (3)
- 2020年7月 (4)
- 2020年6月 (3)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (2)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (3)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (9)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (3)
- 2019年4月 (4)
- 2019年3月 (3)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (5)
- 2018年10月 (2)
- 2018年9月 (54)