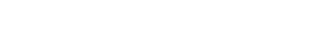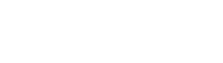- ■
せいぶれいえんコラム
- 2025/07/31
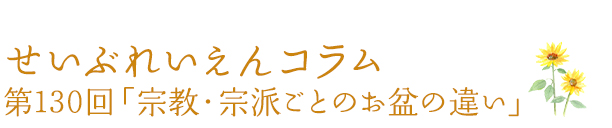
こんにちは、西部霊苑です。お墓参りや季節のことなど、何かのお役にたてる情報を発信していければと思います。
さて7月も終わりが近づき、本格的な夏の暑さにお盆の近さを感じる時期となってきました。
今回は「宗教・宗派ごとのお盆の違い」についてお話しします。
【お盆】
お盆とは日本古来の祖霊信仰と中国の仏教の盂蘭盆会の考え方が融合された文化で、このお盆の時期にはご先祖様の霊が浄土からこの世に帰ってくるとされ、一般的に8月13日から16日までの期間ご先祖様の霊を迎え感謝を伝えるためのさまざまな行事が行われます。
【宗派・宗教ごとの違い】
お盆に行われる風習は宗派・宗教によって違いがみられます。
仏教全般ににおいては一般的に私たちが知るお盆の風習・飾り付けや行事が行われますが、浄土真宗では異なる教えがされています。
浄土真宗では毎年お盆に先祖様をお迎えする風習がなく、初盆にのみご先祖様や故人が唯一帰ってくるとされ、この時に盛大にお盆の行事が行われます。
盆提灯などを飾る風習もなく、代わりに白紋天という白提灯を飾られるようですが、九州などの地方によっては盆提灯が飾られることもあります。
お寺でも故人は無くなって四十九日ののちには仏様となるという教えがあるため、新盆法要も行われず、代わりに歓喜会(かんぎえ)と言われる法話会が行われることがあるようです。
神道では元々お盆の発祥となった祖霊信仰が神道的な思想であるということもあり、神道のお盆も他の仏教と同じようにお盆の風習があります。仏教の仏壇の代わりに神棚や祖霊舎の前に精霊棚を設け、迎え火や送り火を行います。お寺における僧侶に読経のように神道のお盆でも神主による祝詞の奏上が行われます。
キリスト教ではお盆の風習はなく、故人のお墓参りもお盆の期間中に行われることはほぼないようです。
お墓参りは故人の命日などの記念日に行われます。
【地域ごとのお盆の風習】
しかしながら実際のところ、私たち日本人はこうした宗教・宗派を超え地域や文化に根付いた行事、風習を行うことが多いと思います。
たとえば仏教徒などであってもキリスト教の行事であるイエス・キリストの降誕祭であるクリスマスや、神道の行事である初詣や七五三など、多様な考え方を柔軟に受け入れてきました。
お盆の風習についても元々仏教の風習というよりは日本の祖霊信仰と中国の仏教儀式の融合で生まれたものであるため、お寺などではお盆の風習についての考え方、扱い方の違いはあるものの、私たち各家庭では一般的なお盆の風習を行ったり、地域の風習・行事に参加する、また企業や学校でも広く休日とされています。
また時期的な面では全国的には8月中旬がお盆休みですが、お盆の行事自体を行う時期にも地域による違いがあり、関東の一部などでは旧盆として7月中旬に行われます。
これは明治の改暦で旧暦が現在の新暦に変わったことによるもので、旧暦に従い現在の7月にお盆を行うものとする考えで7月に行われています。
この改暦が行われた当時、新暦の7月は農作業をする人が多い地方では非常に忙しい時期であったため、お盆を新盆として8月に行うようになりましたが、商業などを営む人が多かった関東ではそのまま7月にお盆を行っていた名残りがあるためです。
また沖縄などでは9月にお盆の行事を行う場合もあります。
地域ごとのお盆ではその土地その土地の風習や文化の影響を得て独特で様々なものがあり、盆踊りを行う地域や精霊流しや灯篭流しといった行事を行う地域、勇壮な送り火を行う地域、変わったお供えものがされる地域などがあります。
こうした地域に根付いたお盆の風習は懐かしさや心のやすらぎといった望郷の念や、亡くなった家族や大切な人と過ごした日々のことを思い出されてくれ、故人が帰ってきてくれたという暖かい気持ちや故人の冥福を祈る機会となってくれます。
またまとまった休日として取れることもあり、日頃の疲れを取ったり気持ちのリフレッシュのためにこの機会を利用して旅行などに使うこともあり、そうした中では様々な地域のお盆の風習に出会うこともできます。
今年もお盆の時期が近づいてきました。どこか夏の暑さの中にふと気を緩めて心の中を見つめると、忙しい日々に懐かしい日々のことがよぎることがあるかと思います。お盆にはそうした懐かしい人と過ごした時間に思いを馳せるとともに、お墓参りをすることで日頃の感謝を伝える機会としていただければと思います。
それでは次回コラムもよろしくお願いします。

バックナンバー
-
- ■
西部霊苑だより
- 2026/01/30
- ■
-
- ■
せいぶれいえんコラム
- 2025/10/31
- ■
-
- ■
せいぶれいえんコラム
- 2025/10/08
- ■
-
- ■
せいぶれいえんコラム
- 2025/08/27
- ■
-
- ■
せいぶれいえんコラム
- 2025/07/02
- ■
アーカイブ
- 2026年1月 (1)
- 2025年10月 (4)
- 2025年8月 (2)
- 2025年7月 (4)
- 2025年5月 (2)
- 2025年3月 (4)
- 2025年1月 (2)
- 2024年12月 (2)
- 2024年11月 (4)
- 2024年9月 (4)
- 2024年7月 (4)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (3)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (3)
- 2023年10月 (2)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (4)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (3)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (2)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (2)
- 2022年4月 (5)
- 2022年3月 (5)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (3)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (3)
- 2021年3月 (4)
- 2021年2月 (3)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (5)
- 2020年8月 (3)
- 2020年7月 (4)
- 2020年6月 (3)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (2)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (3)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (9)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (3)
- 2019年4月 (4)
- 2019年3月 (3)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (5)
- 2018年10月 (2)
- 2018年9月 (54)