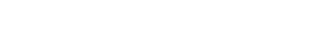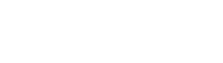- ■
せいぶれいえんコラム
- 2025/08/27

こんにちは、西部霊苑です。お墓参りや季節のことなど、何かのお役にたてる情報を発信していければと思います。
今年のお盆も終わりましたがまだまだ夏の暑さは続いております。9月になると「暑さ寒さも彼岸まで」と言われる秋のお彼岸を迎えることになりますが、皆様も熱中症にはご注意いただき健やかにお過ごしいたければと思います。
さて今年もそうした「秋のお彼岸」について少しお話しさせていただきます。
【秋のお彼岸の時期と意味】
今年の秋のお彼岸は9月20日を彼岸入りとし、23日の秋分の日が中日、26日が彼岸明けとなっています。
このお盆の中日となる秋分の日は天文学的なもので、おおよそ昼と夜の長さが等しくなる日である9月22日から24日頃のうちの1日を国立天文台がその年の秋分の日と定めます。
お彼岸は仏教の思想にある西方浄土の考え方と、日本の農耕文化においてこの時期はちょうど稲などの収穫の時期であることからご先祖様への感謝への気持ちといったことが組み合わさった考え方が元となっています。
こうしたことからお盆の中日となる秋分の日は1948年(昭和23年)に「祖先を敬い、亡くなった人々を偲ぶ。」ための日として国民の祝日に制定されました。
このような由来のあるお彼岸ですので、お墓参りや仏壇のお掃除、お寺の彼岸会法要の参加など先祖様への感謝、ご先祖供養の機会にしていただければと思います。
【初彼岸】
初彼岸(はつひがん)とは、故人が亡くなって四十九日後、初めて迎えるお彼岸のことです。
初盆と同じように故人の初めてのお彼岸になりますので、お供えものや祭壇飾りなど通常のお彼岸のものよりしっかりと揃えられたり、親戚が集まってお経を上げるなどされることがあります。
【お彼岸にやってはいけないこと】
お彼岸にやってはいけないことは特段ないとされていますが、お彼岸はご先祖様供養の弔事の意味もある行事のため、結婚式などの慶事を行うことを気にされる方もいらっしゃいますので、そうしたトラブルを避ける意味で結婚式や引っ越しなどがあまり行われない傾向があります。
【宗派によるお彼岸の違い】
・浄土宗
彼岸会(ひがんえ)と言われ秋分の日とその前後の3日間ご先祖様の供養のためにお墓参りや法要が行われます。
・曹洞宗・臨済宗
浄土宗と同じく彼岸会としてご先祖様の供養のためにお墓参りや法要が行われます。
・真言宗
真言宗も同じく彼岸会、彼岸法要が行われます。
・日蓮宗
お会式と言われ先祖様の供養と自身の修行のため法華経の読誦が行われます。
・浄土真宗
浄土真宗では四十九日を過ぎると仏様になるとされるため、あまりお彼岸についての考え方がされることはないようですが、秋分の日と前後各3日間の7日間に法要会が行われることがあります。
今年の秋分の日は23日の火曜日が祝日、彼岸入りの20日が土曜日、21日は日曜日となっています。
こうした休日・祝日には時間をとれる方も多いかと思いますので、秋の始まりとも言えるお彼岸には少し過ごしやすくなった風を感じながらお墓参りをしていただければと思います。
それでは次回コラムもよろしくお願いします。

バックナンバー
-
- ■
せいぶれいえんコラム
- 2025/10/31
- ■
-
- ■
せいぶれいえんコラム
- 2025/10/08
- ■
-
- ■
せいぶれいえんコラム
- 2025/07/31
- ■
-
- ■
せいぶれいえんコラム
- 2025/07/02
- ■
-
- ■
せいぶれいえんコラム
- 2025/05/28
- ■
アーカイブ
- 2025年10月 (4)
- 2025年8月 (2)
- 2025年7月 (4)
- 2025年5月 (2)
- 2025年3月 (4)
- 2025年1月 (2)
- 2024年12月 (2)
- 2024年11月 (4)
- 2024年9月 (4)
- 2024年7月 (4)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (3)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (2)
- 2023年11月 (3)
- 2023年10月 (2)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (4)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (3)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (2)
- 2022年6月 (4)
- 2022年5月 (2)
- 2022年4月 (5)
- 2022年3月 (5)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (3)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (3)
- 2021年3月 (4)
- 2021年2月 (3)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (5)
- 2020年8月 (3)
- 2020年7月 (4)
- 2020年6月 (3)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (2)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (3)
- 2019年12月 (5)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (9)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (3)
- 2019年4月 (4)
- 2019年3月 (3)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (5)
- 2018年10月 (2)
- 2018年9月 (54)